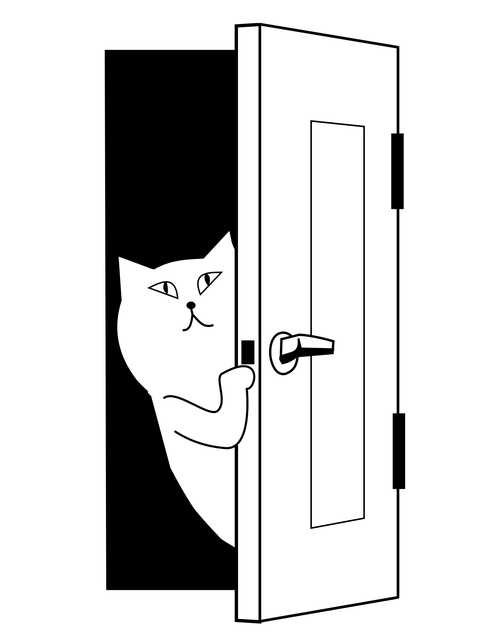私はヨーロッパのドラマが好きで、よく「AXN Mystery」チャンネルを見ています。
アメリカのドラマのように、無駄なラブシーンや騒々しい挿入歌が入ることが少なく、日本のドラマよりも重厚な内容。
(面白いドラマだから日本でも放送されているわけですが、、、)
ある日、ふと目にしたドラマ「ミニチュア作家」の予告。
物語の舞台は17世紀オランダ。アムステルダムの裕福な商人・ヨハネスに嫁いだ少女ネラは、結婚祝いとしてヨハネスから豪華なドールハウスが贈られる。しかし、その謎のドールハウスがネラの生活、そして人生を変えていく…!ミニチュア作家から注文していない小物や人形が次々に届き、戸惑うネラ。しかし、そのミニチュアの小物はまるで家族に起こる出来事を予言しているようだった。そしてじょじょに明らかになる、新しい家族の秘密とはいったい…?!(「AXN Mystery」ホームページから引用)
これは、イギリス人作家Jessie Burton(ジェシー・バートン)(ちなみに、彼女は元女優でとても奇麗な方です)のデビュー作にして、世界的ベストセラーとなった「ミニチュア作家」を、イギリスBBCがドラマ化したもので、しかも、製作総指揮を、「ダウントン・アビー」や「SHERLOCK/シャーロック~忌まわしき花嫁~」など、英国を代表する作品に携わるRebecca Eaton(レベッカ・イートン)が務めるという、超豪華なものです。
とてもおもしろそう、ドラマが放送されるまでに是非とも読んでおかなければと早速購入。
電子書籍は読みたいと思ったときにいつでも購入できるので、とても便利です(その分無駄遣いも増えますが)。
私はamazonのKindleをよく利用しています。
(画像をクリックすると、amazonホームページが開きます。)
この本、おもしろくて、一気に読んでしまいました。
18歳のペトロネラ・オールトマンは、39歳で裕福な商人ヨハンネス・ブラントに嫁ぐため、ただ一人アッセンデルフトの田舎からアムステルダムの大都会へと出てきます。
彼女のお供は、緑色の羽をしたペットのインコ・ペーボだけ。

ネラの心の支えであるペーポ――しかしペーポにも過酷な運命が……
(写真のインコと物語のペーポは関係ありません)
しかし、不安でいっぱいの彼女を出迎えたのは、ブラント家の冷たくがらんとした大理石の床の大きな玄関と、とっつきにくい雰囲気のヨハンネスの姉・マーリン、そして、当時としてはめずらしい黒人の使用人・オットー、メイドとは思えないほど自由な態度で接してくる、ネラより少し年上のコルネリアという、かなり個性的な一家でした。
婚礼の夜だというのに、とても質素な食事。
そして、いつまで経ってもよそよそしい態度のヨハンネス。
ある日、ネラはヨハンネスから彼の家にそっくりな造りの豪華なキャビネットハウス(ドールハウス)をプレゼントされます。
キャビネットハウスというのは、当時裕福な子どもたちが「おままごと遊び」をしながら、食糧庫や寝具の管理、使用人の扱いや家財の管理を学ぶものでした。
ネラは夫からの贈り物に、ひどく子ども扱いを受けているような屈辱感を覚えます。
日々孤独感を募らせていくネラは、ふと知ることとなった「ミニチュア作家」に婚礼の品などの制作を依頼します。
それはある意味、自分を嫁として迎えながら、自分の存在を嫁(館の女主人)として扱わないブラント家の人々へのあてつけのような気持ちでした。
届いた品々は、どれも本物とそっくりで、それは見事なものでした。
しかしやがて、頼んでもいないのに、ネラ自身やブラント家の人々にそっくりな人形、ブラント家に関係する人々の人形やアイテムなどが送られてくるようになります。そして、それらはまるで彼らの未来を予言するような、とても不思議なものでした。
「ミニチュア作家」とは、いったい何者なのか。
なぜネラにそのようなものを送りつけてくるのか。
 アムステルダムの風景
アムステルダムの風景
読み進めていくなかで、物語の冒頭から散りばめられていた様々な伏線が次々と繋がっていきます。
なぜヨハンネスはネラによそよそしい態度をとるのか。
なぜマーリンは他人を寄せつけようとしないのか。
これは、ネラという少女の成長の物語です。
人が精神的な成長を遂げるとき、外部的な要因が果たす役割はとても大きく、不可欠なものです。
いったい何がネラを強くしていったのか。
何故ネラは強くならなければならなかったのか。
そして、これは17世紀という時代を生きる女性たちの物語でもあります。
結婚をしていないマーリンは、本当にみじめな存在なのか。
自由な態度をとるコルネリアを「メイドらしくない」と感じるのは何故なのか。
「ミニチュア作家」は、自身の作品を通し登場人物たちに何を伝えたかったのか。
17世紀のアムステルダムに暮らす人々の、ひたむきで、たくましく、そして残酷な物語が、とても美しい言葉で綴られていきます。
この小説は、本当に言葉がきれいです。
(原作の言葉から美しいのか、翻訳された方の言葉のセンスが良いのか、その両方なのかはわかりません。英語が堪能な方、ぜひ原作と読み比べてみてください。)
物語の冒頭は、お葬式のシーンで始まります。
教会でひっそりと家族を埋葬する女たち、参列するアムステルダムの人々、そして、それを遠くで見つめる一人の人物。
その中を、一羽のムクドリが教会の中へ迷い込みます。外に出してやろうとしても、ムクドリはその気遣いを知ってか知らずか、さらに奥の方へと入っていきます。
「冷えきった教会内部をドアで閉ざし、太陽を振り仰ぎ、環状にめぐらされた運河をたどって海をめざす。ムクドリよ、この建物がどこよりも安全な場所だと信じているのなら、おまえを自由にしてやるのは、このわたしではない。」(本文からの引用)
私はこの美しい文章に、一瞬で心を掴まれました。
そして、この文章は、この物語の全てでもあります。
「わたし」とは誰なのか。
「ムクドリ」は何を表しているのか。
この物語の主人公、ペトロネラ・オールトマンは実在の人物で、彼女のドールハウスもアムステルダム国立美術館に所蔵されています。
 Dolls’ House of Petronella Oortman
Dolls’ House of Petronella Oortman
Licensed under “Copyrighted free use”, via Wikimedia Commons.
ただ、実在のペトロネラ・オールトマンの生涯と、小説に描かれるペトロネラ・オールトマンの生涯は一切関係がありません。あくまで作者Jessie Burton(ジェシー・バートン)が、アムステルダム国立美術館に所蔵されているペトロネラ・オールトマンのドールハウスを見て、この物語の着想を得たものなのだそうです。
Jessie Burtonはイギリスの作家なのですが、17世紀のアムステルダムの様子など綿密な取材のもとに書かれており、読んでいて、美しいだけではないアムステルダムの景色、その中心を流れる運河のにおいまでもが伝わっくるようです。日本の出島も何度か言葉として出てきて、これは日本人としてはうれしい。
読み終えた後、しばらくその不思議な余韻から抜け出すことのできない、とても素晴らしい作品でした。
ぜひ、おすすめの一冊です。
(画像をクリックすると、amazonホームページが開きます。)